不妊治療の平均費用はいくら?治療法別の費用と利用できる助成制度を紹介
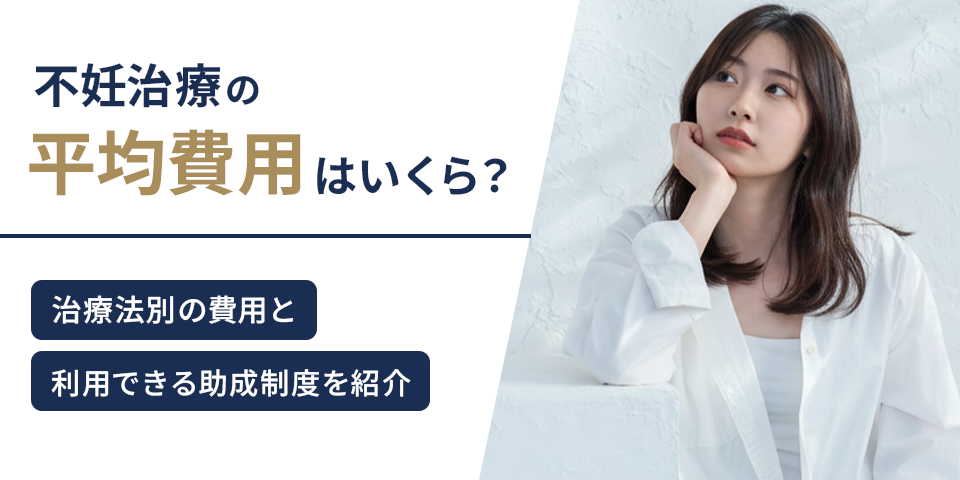
「不妊治療を始めたいけれど、どのくらい費用がかかるのかわからない…」
「不妊治療で使える国の助成制度はあるの?」
このように、不妊治療の費用について不安を感じている方は多いのではないでしょうか。
実際、不妊治療は治療の内容によって費用が大きく異なり、数千円で済むケースもあれば、1回あたり数十万円になることも少なくありません。
この記事では、不妊治療の平均費用や治療法ごとの目安、費用を抑えるために利用できる制度についてわかりやすく解説します。不妊治療の費用に不安を抱えている方は、ぜひ参考にしてください。
不妊治療にかかる平均的な費用とは
不妊治療にかかる費用は、治療法によって大きく異なります。
不妊治療の初期段階で行うタイミング法や人工授精は比較的安価ですが、体外受精や顕微授精などの高度な治療に進むと、1回あたりの費用が数十万円にのぼることも珍しくありません。
以下では、主な治療法ごとの保険適用後の平均的な費用をまとめました。
| 治療法 | 保険適用後の費用目安(1回あたり) |
|---|---|
| タイミング法 | 5,000~8,000円 |
| 人工授精 | 8,000~12,000円 |
| 体外受精 | 100,000~200,000円 |
| 顕微授精 | 120,000~250,000円 |
ここからは、それぞれの治療法ごとにかかる費用を詳しく見ていきましょう。
不妊検査|10,000円~20,000円
不妊治療を始める前に行う「不妊検査」は、妊娠しづらい原因を特定するための大切なステップです。
男女ともに行う検査で、女性の場合はホルモン検査・超音波検査・卵管造影検査など、男性は精液検査が行われます。
検査内容によって費用は変動しますが、保険適用の範囲で受けた場合は1回あたり10,000〜20,000円程度が目安です。
たとえば、ホルモン値の確認や排卵の有無を調べる血液検査は数千円で済むこともありますが、卵管の通りを調べる「卵管造影検査」は1〜2万円前後かかるケースが多いです。
不妊検査は、その後の治療方針を正しく選ぶために欠かせません。検査結果によっては、自然妊娠の可能性が高いと判断され、すぐに治療へ進まず様子を見る選択をすることもあります。
タイミング法|5,000~8,000円
タイミング法は、不妊治療の中でも最も基本的な治療法です。
排卵の時期を正確に予測し、最も妊娠しやすいタイミングで性交を行うことで、自然妊娠の確率を高めます。
費用は1回あたり5,000〜8,000円前後が目安で、超音波検査やホルモン検査、排卵を促す薬の処方などが主な内容です。
保険適用の範囲内で行えるため、自己負担額は比較的少なく、初めて不妊治療を受ける方にとって取り組みやすい方法といえるでしょう。
ただし、排卵誘発剤を併用した場合や、検査内容が追加される場合は費用がやや高くなるケースもあります。
タイミング法は、身体への負担が少ない一方で、確実な成果が出るまでには時間がかかることもあるため、医師と相談しながら継続期間を決めることが大切です。
人工授精|8,000~12,000円
人工授精は、排卵のタイミングに合わせて、精子を直接子宮内に注入する治療法です。
自然妊娠に近い方法でありながら、受精の可能性を高められるため、タイミング法で結果が出なかった場合に選ばれることが多いです。
費用は1回あたり8,000〜12,000円前後が目安で、こちらも保険適用の対象となっています。
ただし、排卵誘発剤の使用や精子の洗浄・濃縮処理を行う場合は、治療内容に応じて追加費用がかかるケースもあります。
なお、人工授精の1回の成功率は5~10%前後といわれており、数回~6回程度を目安に続けるのが一般的です。
体外受精|100,000~200,000円
体外受精(IVF)は、卵子と精子を体外で受精させ、受精卵(胚)を子宮内に戻す治療法です。
タイミング法や人工授精で結果が出なかった場合に選ばれる高度な生殖補助医療で、妊娠率の向上が期待できます。
保険適用後の費用は1回あたり約10万〜20万円が目安です。費用の内訳は、採卵・受精・胚培養・移植といった工程に分かれており、薬の種類や胚の凍結保存などの有無によっても変動します。
顕微授精|120,000~250,000円
顕微授精(ICSI)は、体外受精の一種で、顕微鏡下で1つの精子を直接卵子に注入する高度な治療法です。主に、精子の数が少ない・運動率が低い・受精がうまくいかないといったケースで選ばれます。
保険適用後の費用は1回あたり約12万〜25万円が目安です。
ただし、凍結胚の保存料や一部の検査・薬剤は自由診療扱いとなる場合があるため、治療前に見積もりを確認しておくと安心です。
顕微授精は妊娠率が高い一方で、身体的・精神的な負担も大きいため、パートナーと相談しながら無理のないペースで治療を進めましょう。
不妊治療には保険が適用される
不妊治療は、かつては自由診療として全額自己負担が必要でしたが、2022年4月の制度改正によって、体外受精や顕微授精を含む多くの治療が保険適用の対象となりました。
ただし、すべての治療が保険でまかなわれるわけではなく、適用対象となる治療法や条件が明確に定められています。
また、最新の医療技術を用いた「先進医療」や、一部の検査・薬剤などは保険の対象外となり、自由診療として別途費用がかかる場合もあるので注意が必要です。
ここからは、不妊治療で保険が適用される不妊治療法や条件について、詳しく見ていきましょう。
【関連記事】
不妊治療には保険が適用される!条件や範囲、メリット・デメリットを解説
保険が適用される不妊治療法
不妊治療で保険が適用されるのは、医師が「医学的に必要」と判断した場合に行う一般不妊治療と生殖補助医療(ART)です。
主な治療法としては、以下のようなものが挙げられます。
- 不妊検査
- タイミング法
- 排卵誘発剤の使用
- 人工授精(AIH)
- 体外受精(IVF)
- 顕微授精(ICSI)
- 一部の胚凍結・融解移植やホルモン療法
また、これらの治療が指定医療機関で実施されることも保険適用の条件です。
一方で、タイムラプス培養、PGT-A検査などの先進医療は保険の対象外となるため注意しましょう。
保険適用の条件
不妊治療の保険適用には、治療法ごとに一定の年齢・回数制限が設けられています。
特に体外受精や顕微授精といった生殖補助医療(ART)は、年齢によって保険が適用される回数が以下のように異なる点に注意しましょう。
| 女性の治療開始時の年齢 | 保険適用回数の上限 |
| 40歳未満 | 6回まで |
| 40歳以上〜43歳未満 | 3回まで |
| 43歳以上 | 適用なし |
なお、ここでの「1回」とは、採卵から受精・胚移植までの一連の治療プロセスを指します。採卵や受精などの工程ごとにカウントされるわけではない点に注意が必要です。
また、タイミング法や人工授精といった一般不妊治療については、年齢や回数の制限は設けられていません。
不妊治療の費用を抑えるために使える制度
不妊治療を行う方の中には「お金が続かない」といった理由で治療を諦めてしまう方も少なくありません。
そこで、不妊治療による費用負担を少しでも抑えるためには、保険適用を受けることはもちろん、以下のような制度を利用することも大切です。
- 医療費控除
- 高額療養費制度
- 各自治体の不妊治療助成制度
ここでは、それぞれの制度について詳しく見ていきましょう。
医療費控除
医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が10万円を超えた場合、確定申告によって10万円を超えた分を所得から差し引ける制度です。
これにより、所得税や住民税の負担が軽くなり、実質的に不妊治療による負担を減らすことができます。
控除の対象となるのは、体外受精や顕微授精といった高度な不妊治療だけでなく、タイミング法や人工授精、検査費、薬代、通院交通費なども含まれます。
ただし、医療費控除を受けるには、確定申告の際に領収書や明細書を提出しなければなりません。そのため、不妊治療を始めたら、治療費の領収書や薬局のレシートをすべて保管しておくことが大切です。
高額療養費制度
「高額療養費制度」とは、1ヵ月に支払った保険診療分の医療費が高額になった場合に、自己負担額の上限を超えた分が払い戻される制度です。
不妊治療は1回あたりの費用が高くなりやすいため、この制度を上手に活用することで実質的な負担を軽減できます。
上限額は所得によって異なりますが、たとえば年収370万~770万円の世帯では、1カ月の自己負担上限は約8万円程度です。そのため、もし1回の治療で15万円支払った場合、差額分の約7万円が後日払い戻されることになります。
別途申請は必要ですが、高額な治療費が不妊治療をためらう要因となっている場合は、利用しない手はないでしょう。
各自治体の不妊治療助成制度
不妊治療の費用をさらに抑えたい場合は、自治体が実施している助成制度を活用するのも有効です。
国の保険適用とは別に、各自治体によっては独自の支援事業を設けており、不妊検査や人工授精などの費用を一部助成してもらえることがあります。
こうした助成事業を上手に組み合わせることで、実質的な負担をさらに減らすことが可能です。
なお、埼玉県では2025年10月現在不妊治療に関する助成事業を行っていません。そのため、国の制度以外で不妊治療による費用負担を抑えるためには、民間保険への加入などを検討する必要があります。
まとめ
不妊治療の平均費用は、治療の内容によって大きく異なりますが、1回あたり数千円~20万円前後が目安といえるでしょう。
現在では不妊治療にも保険が適用されるため、以前と比べて自己負担額は大幅に低くなっています。
また、医療費控除や高額療養費制度などを活用すれば、費用負担をさらに抑えることもできるでしょう。
とはいえ、不妊治療全体を通じた総額については個人差があるため、明確な相場というものはありません。
具体的な費用については医療機関とも相談し、あなたのペース・予算に合った方法で治療に取り組んでみてくださいね。

