体外受精は保険適用の対象!条件や回数、注意点について
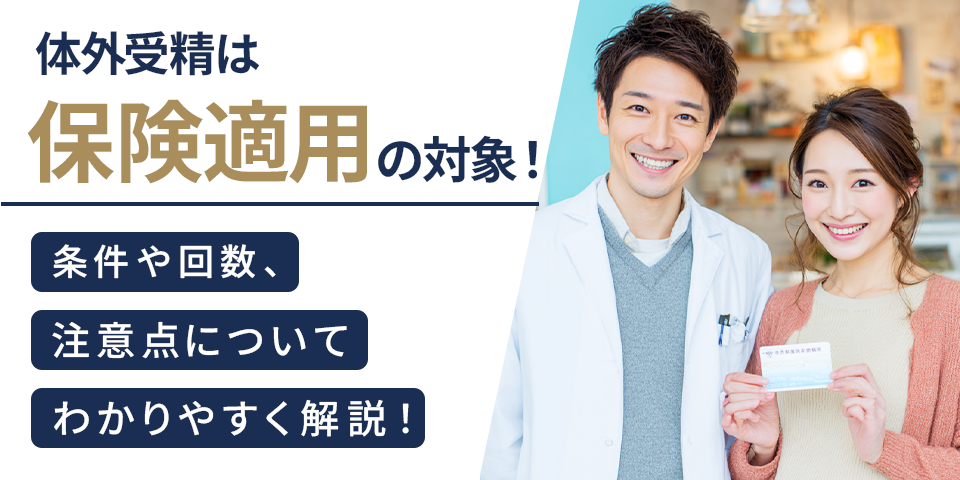
「体外受精に保険が適用されるようになったって聞いたけど、本当?」
「年齢制限があると聞いたけど、うちは対象になるのかな…」
不妊治療として体外受精を検討されている方の中には、こうした疑問や不安を感じている方も多いのではないでしょうか。実際、2022年4月から体外受精を含む一部の不妊治療が保険適用の対象となり、費用負担が大幅に軽減されました。
ただし、保険を使うには年齢や治療回数など、いくつかの条件があります。
本記事では、体外受精の保険適用に関する制度の概要から、対象となる条件、費用の目安、保険適用外となった場合の対応策までをわかりやすく解説します。
将来に向けて安心して治療に向き合うために、ぜひ参考にしてみてください。
体外受精は保険の適用対象
体外受精は以前まで全額自己負担であったものの、2022年4月から健康保険の適用対象となっています。そのため、現在では不妊治療として体外受精を行う場合、原則3割の自己負担のみで治療を受けることが可能です。
保険適用の対象となる治療は、医師が「医学的に妊娠の可能性がある」と判断したケースで、一定の年齢制限や治療回数の上限がありますが、多くの夫婦が保険の対象となる可能性があります。
なお、保険適用を受けるには、認定を受けた医療機関での治療が必要となるため、事前に確認しておきましょう。
また、詳細な制度内容については、厚生労働省の資料「令和4年4月から、不妊治療が保険適用されています。」でも確認できます。
体外受精以外で保険が適用される不妊治療
現在では、体外受精以外に以下のような不妊治療が保険適用の対象となっています。
- タイミング法(排卵時期の指導など)
- 排卵誘発剤の使用
- 人工授精(AIH)
- 顕微授精(ICSI)
- 受精卵(胚)・精子の凍結および融解
- 一部の薬剤によるホルモン治療
また、体外受精と併用されることの多いタイムラプス撮影やPICSIなどの「先進医療」は、原則として保険診療と同時に受けられる「選定療養」という形で扱われます。
この場合、先進医療の部分だけが自己負担となり、他の部分は保険適用の対象となります。
なお、ここで注意したいのが「混合診療(保険と自由診療の併用)」です。保険診療の中に自由診療を含めてしまうことは原則として認められておらず、その場合はすべての治療が自由診療扱いとなってしまいます。
体外受精をほかの治療と併用する場合は、保険適用になるかどうかを医師に確認することを徹底しましょう。不妊治療の選択肢は体外受精以外にも幅広いため、治療内容ごとに保険適用の可否を確認することが大切です。
体外受精が保険適用される条件
体外受精が保険で受けられるようになったとはいえ、すべての人が制限なく治療を受けられるわけではありません。体外受精を含む不妊治療の保険適用には、年齢によって以下のような治療回数の条件が設けられています。
| 年齢区分 | 保険適用の上限回数 | 備考 |
|---|---|---|
| 40歳未満 | 6回まで | 治療中に40歳を超えても、6回まで保険適用が可能 |
| 40歳以上43歳未満 | 3回まで | 治療開始前に43歳を迎えると新規治療への保険適用は不可 |
なお、年齢のカウントは「治療を開始した日」で判断されるため、39歳で始めた場合は40歳を超えても最大6回の保険適用を受けられます。
また、42歳で治療を始めた場合、43歳を過ぎても3回までの保険適用を受けることが可能です。
体外受精の「1回」はどこでカウントされる?
体外受精における保険適用の「1回」とは、胚移植を1回行った時点で1回分としてカウントされます。採卵や受精、凍結までは何度実施してもカウントには含まれず、胚移植を実施したタイミングで「1回」となることを覚えておきましょう。
また、治療後に出産まで至った場合は、それまでの回数はリセットされ、再度保険適用の枠が利用可能になります。治療計画を立てる際は、どの時点で「1回」と数えられるのかをしっかり理解しておきましょう。
2022年4月以前から不妊治療を行っている場合も保険適用が可能
2022年4月の制度改正以前から不妊治療を続けていた場合でも、上記の条件を満たせば保険適用を受けることができます。
つまり、過去に自由診療で体外受精を行っていた方も、年齢と治療回数の条件に該当すれば、2022年4月以降の治療から公的医療保険を適用することが可能です。
なお、上限回数については、通算ではなく保険適用分のみカウントされます。
たとえば、制度改正前に自由診療で3回体外受精を行っている場合でも、現在40歳未満であれば保険適用でさらに6回まで治療が可能です。
体外受精が保険適用となったことによるメリット
経済的な理由から不妊治療を諦めていた夫婦にとって、体外受精の保険適用は大きな支えとなる制度といえるでしょう。
ここでは、体外受精の保険適用によって得られる以下2つのメリットについて解説します。
- 不妊治療にかかる自己負担額が減る
- 高額療養費制度を利用できる
それぞれのメリットについて、詳しく見ていきましょう。
不妊治療にかかる自己負担額が減る
体外受精が保険適用となったことで、治療費の自己負担がこれまでの全額負担(自由診療)から、原則3割負担にまで軽減されました。
体外受精には1回あたり約40万〜60万円程度の費用がかかりますが、保険適用によって約10万〜20万円前後にまで費用を抑えることが可能です。
また、治療に使用する薬剤や事前検査も保険適用の対象となるため、治療にかかる費用総額を大幅に抑えられる点も大きなメリットといえます。
このように、経済的な負担が軽くなることで「費用がネックで体外受精を迷っていた」という方も前向きに検討しやすくなるでしょう。
高額療養費制度を利用できる
体外受精が保険適用となったことで、「高額療養費制度」を利用できるようになったことも大きなメリットとして挙げられます。
高額療養費制度とは、1ヵ月の医療費が一定の上限額を超えた場合に、超過分が払い戻される仕組みのことです。
たとえば、年収が約370万〜770万円の方であれば、自己負担の上限は1ヵ月あたりおおむね8万円前後に抑えられます。体外受精などの不妊治療には高額な治療費がかかるケースも多いので、高額医療費制度を利用できるメリットは大きいでしょう。
ただし、払い戻しには申請手続きが必要なため、事前に医療機関や保険者に確認しておくと安心です。
体外受精が保険適用となったことによるデメリット
体外受精が保険適用となり、費用負担が軽減された一方で、2022年4月以降は「特定不妊治療助成制度」が廃止されている点には注意が必要です。
特定不妊治療助成制度では、1回あたり最大30万円が支給されるケースもあり、高額な自由診療を選択する方にとっては大きな支援となっていました。
現在は保険適用により、医療費の自己負担は原則3割に抑えられていますが、場合によっては、助成制度を利用していた時期よりも実質的な負担が増えるケースもあります。
たとえば、体外受精1回の費用が30万円だった場合、助成制度があったころは全額補助されることもありましたが、保険適用では3割にあたる約9万円が自己負担となります。
このように、制度の違いによって負担の感じ方が変わる点は押さえておきましょう。
旧制度で助成金を受け取った人も保険適用は可能
2022年3月まで実施されていた「特定不妊治療助成制度」を利用していた場合でも、現在の保険適用制度を使うことは可能です。助成金をすでに受け取っていたとしても、それによって保険診療の対象外になることはありません。
たとえば、過去に自由診療で複数回治療を行い、助成金を受け取っていた方でも、年齢や回数などの条件を満たせば、2022年4月以降の治療から保険を適用することは可能です。
ただし、保険で受けられる治療回数には年齢に応じた上限があるため、これまでの治療歴にかかわらず、今後の治療計画は慎重に立てることが大切です。迷ったときは、医療機関で制度について相談してみましょう。
体外受精で保険適用回数を超えるとどうなる?
体外受精における保険適用には、年齢に応じた回数制限があります。具体的には、40歳未満で最大6回、40歳以上43歳未満で最大3回までが保険の対象です。
そのため、この上限回数を超えた場合、以降の治療はすべて自由診療(自費診療)となります。自由診療では体外受精1回あたりの費用が40万〜60万円、場合によってはそれ以上になることもあり、経済的負担は一気に増加します。
保険適用回数の上限は通算でカウントされるため、「あと何回使えるのか」は治療計画を立てるうえで非常に重要です。不安がある方は、医師と相談しながら早めに全体の治療方針を見直すことをおすすめします。
保険適用以外で体外受精の費用を抑える方法
保険適用の回数を超えた場合や、自由診療での治療を選択する場合でも、費用負担を軽減する方法はいくつかあります。とくに民間保険や自治体の助成制度は、利用できると大きな支えになります。
以下に代表的な制度をまとめましたので、治療前に一度確認しておきましょう。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 民間医療保険 | 不妊治療特約や先進医療特約付きの保険に加入していれば、一部費用を補償してもらえる場合がある。 |
| 自治体の助成金制度 | 自治体によっては独自に不妊治療助成を継続しているところもあり、所得制限や年齢条件に応じて数万円〜十数万円の補助が出る場合がある。 |
ただし、これらの制度は住んでいる地域や加入している保険によって利用可否が異なるため、必ず事前に確認・相談しておくことが大切です。
まとめ
本記事では、体外受精の保険適用について、条件や注意点などを詳しく解説しました。体外受精は2022年4月以降、保険の適用対象となっており、不妊治療に取り組む夫婦にとっての経済的な負担が大きく軽減できるようになっています。
ただし、保険適用には年齢や回数などの条件があるため、制度の内容を正しく理解しておくことが大切です。
また、保険適用以外にも体外受精の費用負担を抑える方法はあるので、医師や自治体に相談しながら、自分たちにとって最適な選択をしましょう。

